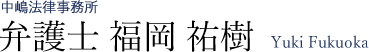不当解雇とは?企業側が知っておくべきポイントを解説
不当解雇とは
解雇とは、企業側から一方的な意思表示により労働契約を解約することをいいます。
そして、「不当解雇」とは、法律や就業規則に違反してされた解雇のことをいいます。具体的には、労働契約法に違反してなされた解雇、労働基準法に違反してなされた解雇、就業規則に定められている手続に違反してなされた解雇が挙げられます。
不当解雇かどうかについては、最終的に裁判所が判断することになりますが、不当解雇であると判断された場合は、解雇は無効となります。解雇が無効となると、解雇後も雇用契約が継続しているものとされ、企業は労働者を雇い続けなければならないばかりか、解雇時に遡って賃金の支払を命じられます。これは企業にとって大きな負担となりますので、企業としては、不当解雇にならないように慎重な対応が求められます。
不当解雇にならないようにするためには、労働契約法について知っておくことが重要です。労働契約法では、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとされています(労働契約法16条)。つまり、不当解雇にならないためには、解雇に客観的に合理的な理由が認められ、かつ社会通念上相当と認められる必要があります。
では、どのような場合が不当解雇となり得るのでしょうか。以下では、実務上、問題となりやすい能力不足解雇と協調性の欠如による解雇について解説していきます。
能力不足による解雇
企業からのご相談として多いのが、能力不足を理由とする解雇です。
労働者は、労働契約に基づき、賃金に見合った適正な労働を提供する義務を負います。そのため、労働者に職務遂行能力、適格性の欠如・不足や勤務成績の不良がある場合、労働義務の不完全履行とされ、解雇理由となります。
過去の裁判例では、単に労働者の職務遂行能力等が低いだけでは足りず、能力が著しく低く、指導や教育などにより、向上や改善の見込みがない場合に、解雇を有効としているものが多いといえます。
もっとも、能力不足の判断については、新卒採用か否か、地位を特定した中途採用かどうか、専門職かどうか、管理職かどうか、企業の規模などによって異なってきます。
新卒採用の場合には、職務経験や知識の乏しい労働者を若年のうちに雇用し、多様な部署で教育しながら職務を果たさせることを前提とするため、能力不足があったとしても解雇前に十分な指導教育や配置転換等が求められるなど、解雇は比較的厳格に判断される傾向にあります。
一方、地位を特定した中途採用、専門職、管理職などは、その職責上、一般労働者よりも高度の専門知識や能力と思い職責を求められることから、期待される職責と実績との乖離がある場合、解雇は比較的緩やかに判断される傾向にあります。
また、企業規模によって、指導教育や配置転換がどの程度期待できるかについても異なります。大規模な企業であれば、教育体制が充実しており、多くの部署が存在することから、十分な指導教育や他部署に配置転換を行うことが求められることが多いと思われますが、小規模の企業に同じレベルの指導教育や配置転換は期待できないことも多いでしょう。
能力不足解雇で裁判となった場合、裁判所が、日ごろから労働者と接していた企業とは異なり、労働者の能力や適格性を評価することやどのような指導教育がなされているかを認定すること困難が伴います。
そのため、会社としては、これらを立証できるように、日常の労務管理において、日報、クレーム報告書、社内議事録、面談記録、メール、注意書、始末書、反省文、研修受講票、人事評価書など、書面などの客観的な証拠を残しておく必要があります。
特に、本人の作成した日報や始末書、反省文、メールなどは、本人の認識や本人とのやりとりの経過が分かることが多いため、作成することをお勧めします。
協調性の欠如を理由とする解雇
能力不足を理由とする解雇と並んで、企業からのご相談として多いのが、協調性の欠如を理由とする解雇です。
労働者は、企業という組織・集団内で働く以上、上司や労働との協調性にも配慮して行動することが求められます。そのため、労働者の協調性を欠く言動により、業務に著しい支障を生じさせている場合は解雇理由となり得ます。
過去の裁判例では、労働者が自己の方法やスケジュールに固執して会社の指示に従わないために業務上の混乱を招き改善を見られない場合(東京地判平成6年3月11日労判66号61頁)、職制や会社批判等の問題行動を繰り返し職場の軋轢を生じさせた場合(東京地判平成19年9月14日労判1073号11頁)、自らの思い込みに基づいて攻撃的で非常識なメールを多数送信する等の行為を繰り返した場合(東京高判平成25年3月21日労判1079号148頁)などで、解雇が有効とされています。
協調性の欠如による解雇についても、能力不足による解雇と同様、指導や教育などにより、向上や改善の見込みがないことが求められることが多いので、企業が労働者について協調性を欠いていると判断したものの、十分な指導や配置転換などの調整を行わずに解雇とする場合には解雇が無効となる可能性が高まります。なお、企業の規模により求められる措置が異なることは能力不足解雇の場合と同様です。
能力不足解雇の場合と同様、後に労働者とトラブルとなった場合に備えて、日常の労働管理において、客観的か証拠を残しておく必要があります。
以上が不当解雇の代表例と、その際に企業側が知っておくべきポイントです。企業としては、従業員をやむを得ず解雇せざるを得ないこともありますので、不当解雇にならないよう十分に注意して行うことが必要です。
弁護士・福岡 祐樹(中嶋法律事務所)は、債権回収のほか、介護事業トラブル、不動産トラブル、企業法務などを中心に取り扱っております。新宿区、渋谷区、中央区、文京区、千代田区、江東区などで事業を行っている方を中心にご相談を受けております。お気軽にご相談ください。
MAIN KNOWLEDGE
弁護士 福岡祐樹が提供する基礎知識
-

リーガルチェックの重...
「中小企業のため、特別な契約については取引先から契約書を提示してもらっているが、リスクとなっていないだろうか。」 「取引にあたって契約書を提示したところ、修正の依頼をされてしまった。依頼内容に問題がないかどうかどのように […]
-

不動産相続トラブル
不動産の相続に際しては様々な問題が発生する恐れがあります。具体的には不動産の資産価値の把握、不動産の分割方法に関して問題となることが多いです。 ■不動産の資産価値の把握 相続をする際の相続財産の把握及び遺産 […]
-

債権回収の方法と流れ
債権回収の流れとしては、基本的に以下のようになります。 (1)任意的な方法による債権回収債権を回収する場合、いきなり訴訟で解決しようとするのではなく、まずは当事者の話し合いで解決できないかを探ることになります。 […]
-

借地借家トラブル
不動産経営を行う際には賃料の滞納、賃料の増減額などの様々な借地借家トラブルが発生する恐れがあります。 ■賃料の滞納 賃料の滞納の際には、まずは相手方に対して賃料支払の督促状を送付します。それでも賃料の支払い […]
-

悪質なカスハラに困っ...
■カスタマーハラスメントとは カスタマーハラスメントは、企業の業務の妨害になるほか、対応する従業員の精神的負担にもなるため、毅然とした対応が求められます。 企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることから、カス […]
-

強制執行(差押え)の...
強制執行とは、お金を支払わない債務者や、不動産を明け渡さない債務者に対して、裁判所が請求を強制的に実現する手続きのことをいいます。強制執行をするためには、債務名義を得る必要があります。債務名義は、裁判で勝訴判決を得た場合 […]
SEARCH KEYWORD
よく検索されるキーワード
-
- 不動産トラブル 弁護士 相談 新宿区
- 顧問弁護士 弁護士 相談 新宿区
- 介護事業トラブル 中央区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 牛込神楽坂
- 不動産トラブル 弁護士 相談 文京区
- 債権回収 弁護士 相談 渋谷区
- 法律問題 弁護士 相談 千代田区
- 不動産トラブル 弁護士 相談 神楽坂
- 介護事業トラブル 弁護士 相談 飯田橋
- 債権回収 弁護士 相談 江東区
- 法律問題 弁護士 相談 飯田橋
- 法律問題 弁護士 相談 新宿区
- 企業法務 弁護士 相談 神楽坂
- 企業法務 弁護士 相談 江東区
- 介護事業トラブル 弁護士 相談 江東区
- 顧問弁護士 中央区
- 法律問題 弁護士 相談 神楽坂
- 債権回収 弁護士 相談 神楽坂
- 債権回収 弁護士 相談 千代田区
- 企業法務 中央区
LAWYER
弁護士紹介
弁護士 福岡祐樹
- 所属団体
- 第一東京弁護士会
- 注力分野
-
債権回収
介護事業(経営側)
不動産
企業法務
- 執務方針
- 依頼者の皆様のご依頼、ご要望を最大限実現するために、誠実に粘り強く取り組みます。
- 経歴
-
2002年3月 香川県立高松高等学校 卒業 2006年3月 東京大学法学部 卒業 2008年3月 東京大学大学院法学政治学研究科 卒業 2009年12月 弁護士登録(62期)
田辺総合法律事務所入所
2013年3月 民間企業へ社内弁護士として出向(2016年3月まで) 2016年4月 中嶋法律事務所入所
- 著書・講演 等
-
『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』(清文社・共著)
『会社が労働審判手続を申し立てられた場合の実務対応』
(BUSINESS LAW JOURNAL 2012.3 No.48)
『病院・診療所経営の法律相談』(青林書院・共著)
『企業間契約交渉におけるトラブルと実務上の留意点~契約締結上の過失を中心に~』(BUSINESS LAW JOURNAL 2014.4 No.73)
『わかりやすい保育所運営の手引-Q&Aとトラブル事例-』
(新日本法規・共著)
『逐条 破産法・民事再生法の読み方』(商事法務・共著)
OFFICE
事務所概要
| 名称 | 中嶋法律事務所 弁護士 福岡祐樹(ふくおかゆうき) |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0832 東京都新宿区岩戸町7番地1 牛込神楽坂駅前ビル5F |
| TEL | 03-3260-3620 |
| FAX | 03-3269-1300 |
| 営業時間 | 9:30-18:00 ※時間外も対応可能です(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝 ※休日も対応可能です(要予約) |